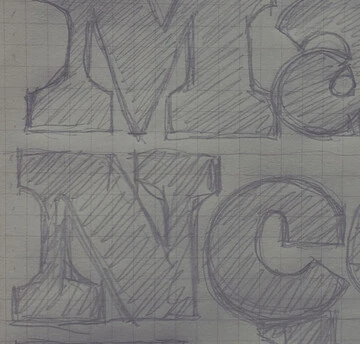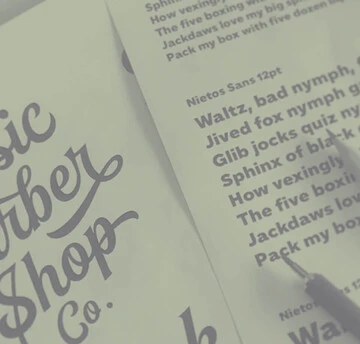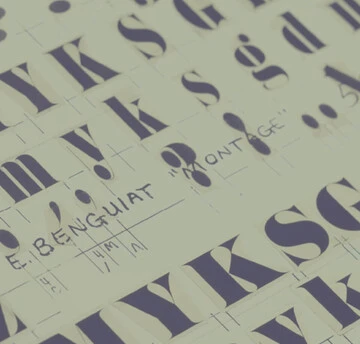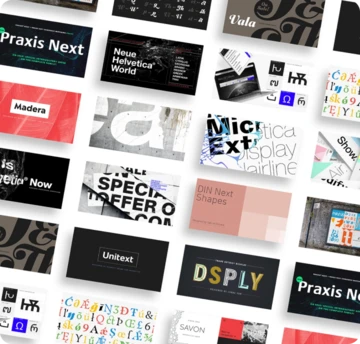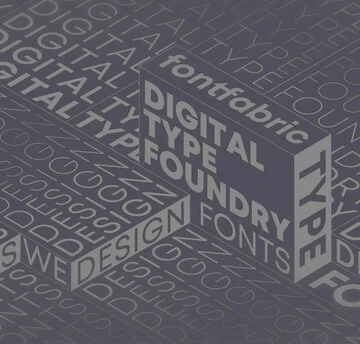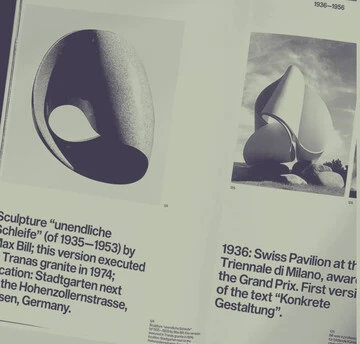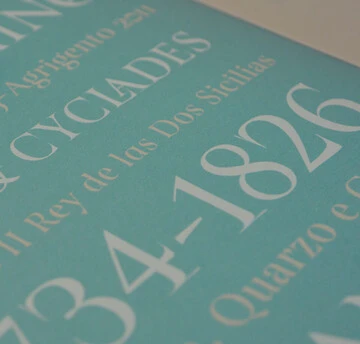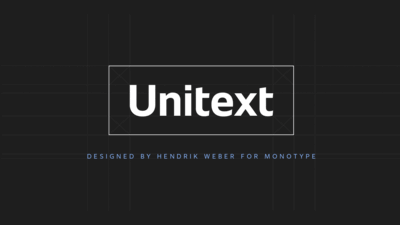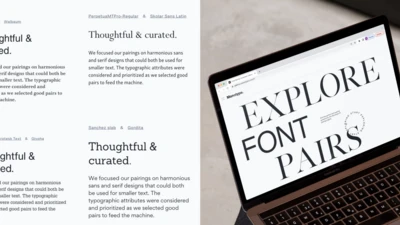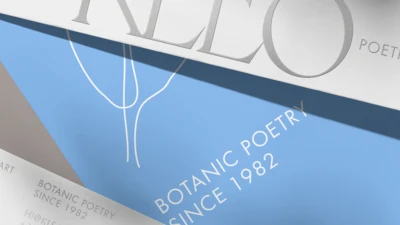店舗とは何か?ロックダウン時代の小売業の再考.

2020年の前半から学んだことがあるとすれば、世界的なパンデミックの中で生活し、ビジネスを運営することは予測可能性がほとんどないということです。自主隔離の実践、長期の外出自粛要請、ウイルスが公共の場でどのように広がるかという認識の急速な変化により、COVID-19は人々の購買行動を根本的かつ不可逆的に変えました。
不要不急の店舗は閉鎖されました。そして、必需品を扱う店舗を訪れる顧客は、「必要なものを迅速かつ効率的に手に入れ、可能な限り少ない人との接触で済ませる」という目的を持って入店するようになりました。
その結果、アメリカのオンライン小売業の規模は前年比で68%増加しました。パンデミック前からオンラインで買い物をしていた人々はさらに利用を増やしており、遅れてオンラインショッピングを始めた人々も初めて試し、その利便性に気づいている可能性があります。経済活動が再開し、店舗での買い物が可能になったとしても、顧客は感染への恐れ(ワクチンが普及したとしても)や、単純に物理的な店舗で買い物をする必要がなくなったことから、以前の購買行動に戻らないかもしれません。その代わりに、食料品、衣料品、薬局商品、エンターテインメントに至るまでの購買行動がオンラインに移行し、長期的に店舗やモールへの訪問を置き換える可能性があります。そして、これはショッピングモールに依存した従来型の小売業の衰退をさらに加速させています。
——ここで改めて問う必要があります。「店とは何のためにあるのか?」
従来の実店舗型小売業の衰退.
もはや明白ですが、小売業がCOVID-19以前の「通常」の状態に戻ることはないでしょう。新たな消費者の行動は、小売業の運営方法や存在意義そのものに影響を及ぼしています。現在、店舗はより衛生的で、合理化され、非接触型の体験を提供するために、店舗空間の再設計に注力しています。
Fast Companyは、顧客が気軽に商品を見て回る傾向が減ると予測しています。ブランドは、顧客が商品を試したり、商品を探すための場所ではなく、オンラインで注文した商品を受け取ったり(カーブサイドピックアップ)、返品・交換したり、店員からサポートを受けたりできる場所として店舗を再構築していくでしょう。
これは必ずしも新しいコンセプトではありません。Postmatesのようなサービスが宅配や受け取りを一般化し、より多くの店舗がオンライン購入と店頭受け取りの注文オプションを提供し、スーパーマーケットの配送サービスも普及しています。これまでとの違いは、これらの方法がビジネスの中心的な存在になっていくという点です。
Starbucksでは、パンデミックにより、注文受け取り専用の「ピックアップ店舗」を含む店舗モデルへの移行が加速しました。一部の既存店舗では、人々がリラックスできるカフェ形式の店舗を置き換える形で展開されています。顧客ニーズの変化に対応するためのこの数十億ドルの規模となる戦略は、当初3~5年かけて展開される予定でしたが、新たな需要の高まりにより、今すぐにでも移行が不可欠となっています。多くの顧客は、カフェが再開しても座って社交したり仕事をしたりすることを望まなくなっています。これはパンデミック中に彼らの習慣やルーティンが変わったため、あるいは混雑したカフェの環境に快適さを感じなくなっているためです。同社はパンデミックにより、職場や家庭とは別の「サードプレイス」としてのコンセプトを再考せざるを得なかったと述べています。今後、多くの顧客はコーヒーを受け取ってすぐに立ち去りたいというニーズが主流になると見られています。
Fast Companyは、小売におけるスタッフと顧客の関係性がさらに重要になると報告しています。顧客が店舗に電話して製品について問い合わせ、その後、スタッフが自宅で試せる商品を選定・提案するようなパーソナルショッピングがより人気を得る可能性があります。オンラインの注文を単に処理するだけでなく、パーソナルな提案力が重要になるでしょう。
安全な環境の提供も優先事項となります。小売業の従業員は、製品や表面の定期的な消毒の責任を負うことになります。目に見える安全対策は、消費者が物理的な店舗での買い物に戻る際の不安を和らげる可能性があります。EC決済企業Fastの調査によると、89%の買い物客は物理的な空間での買い物に不安を感じています。調査回答者の63%が最も心配しているのは「他人と近すぎる距離」で、40%は店舗の清潔さに最も懸念を抱き、34%はPOS端末に触れることに警戒し、32%は現金の取り扱いに不安を感じています。
店舗は、顧客がより効果的にソーシャルディスタンスを保てるように空間を再設計し、ディスプレイを撤去したり、床に誘導表示を施したりする場合もあります。アパレル業界では試着室を再開すべきかどうかの判断に苦慮しています。そしてもちろん、入店人数を制限する必要があります。
物理的な空間を再考すると同時に、多くのブランドは販売を維持するために新たなデジタルチャネルを活用または導入しています。例えば、PepsiやFrito-Layは顧客が直接スナックを購入できるDTC(Direct-to-Consumer)サイトを立ち上げました。これにより、従来店舗での衝動買いの体験を、オンラインに移行して補っています。
多くのブランドがデジタルプラットフォームへの投資を増やしており、例えば製品の注文・配送・店舗受取に対応したウェブサイトの改善に力を入れています。地域に密着したビジネスでは、醸造所やワインバーがタップルームでの販売を置き換えるために、新しいオンライン注文プラットフォームを構築するケースも見られます。他のブランドもモバイル体験への投資を続けています。
Shopify Retailのプロダクト責任者であるArpan Podduturiは、小規模から中規模の企業がPOSソリューションを通じてオンラインで製品を販売できるよう支援するプラットフォームについて、次のように述べています。「私たちの目標は、小売業者が店舗を超えて販売を継続できるよう支援することです。厳しい小売環境でも、店舗への客足が少ない場合でも売上を維持し、消費者の流れが戻った際には売上を伸ばすことができるような環境を整えることが重要だと考えています」
デザインが果たす役割.
人々、そしてブランドがデジタル中心の体験へと急速に移行する中、人間味あふれるオンラインプレゼンスは大きな違いを生み出すでしょう。それは、温かみがあり、素朴で、誠実で、手作り感を感じさせるデザインのディテール(例えば、暖色系の色調、色調を強調した写真、人物を起用したイメージ、魅力的なセリフ体のフォントなど)を通して表現されるかもしれません。あるいはユーザー体験そのものにパーソナライズされた要素を取り入れることも重要です。機能や取引だけの関係ではなく、パーソナルで感情的な体験が求められています。
実店舗での気軽な買い物はなくなっていくかもしれません。そのため、ブランドのWebサイトは、ショーウィンドウや販売スタッフとのやり取りなど、実店舗での体験を模倣するように、オンラインストアの体験を再構築することを検討すべきでしょう。チャットボットではなく人間とのライブチャットやビデオ通話が増えたり、販売スタッフがキュレーションしたコンテンツをWebサイトやSNSで展開する動きも増えていくかもしれません。
ブランドによっては、閲覧データや嗜好に基づいてショッピング体験のパーソナライゼーションを強化する可能性があります。ブランドが顧客にとってより関連性の高い商品や、パーソナルな興味関心を予測する能力は、平均注文額(AOV)や注文ごとの商品点数(IPO)の向上に直結する可能性があります。
オンラインと実店舗におけるブランド体験には、一貫性が不可欠です。それぞれのプラットフォームの目的が異なるとしても(オンラインは閲覧や購入のため、店舗は予約、受け取り、返品のためなど)、統一されたタイポグラフィ戦略によって、それらを一体化し、シームレスなユーザージャーニーを提供することができます。顧客がどこでブランドと接点を持ったとしても、ブランドの一貫性や、そのプラットフォームの目的が顧客にとって明確であるべきです。統一されていないアプローチでは、顧客が混乱を感じる可能性があります。
私たちは、ブランドと顧客にとって未知の領域に足を踏み入れようとしています。この小売業が直面している新しい現実で、何が機能するのかを見つける唯一の方法は、多くのアプローチを試すことです。ブランドが顧客とつながる方法を見つけるまで、成功と失敗を繰り返すことが重要です。それは単なるニーズの充足にとどまらず、感情のレベルで顧客とつながることが求められているのです。