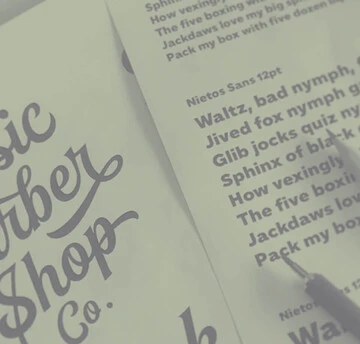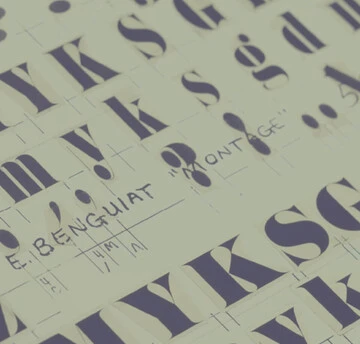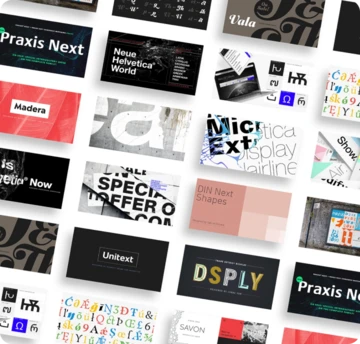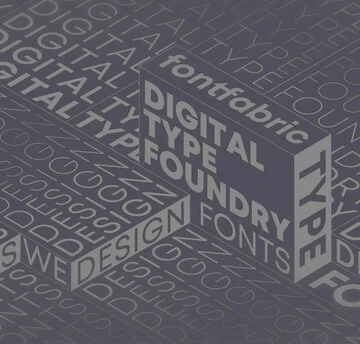Good Type part 4:良い書体は、それだけで魅力を放つ.
フォントは単なる道具ではありません。デザイナーにとってはツールの一つでありながら、単なる実用性を超え、人の感情に強く訴えかける力も備えています。フォントが、ビジュアルコミュニケーションの課題を解決する鍵になるでしょう。
ディスプレイフォント(見出し用途に用いられる書体)には、本文用の書体とは異なる役割があります。ディスプレイフォントは、可読性の限界を超えたり、注目を集めたり、ユーザーを魅了したりする能力があります。多くの場合、そうしたフォントの持つアイデンティティや時代感は強力な効果を持ち、見る人を即座に特定の時代へと運んだり、ある感情や記憶を呼び 起こしたりすることができます。
こうした自由な表現ができるのは、ディスプレイフォントが歪みや質感といった加工にも柔軟に対応できるからです。通常の本文では、一定の制約の下で可読性が最優先されます。しかし、ディスプレイフォントにおいては、そのフォルムの実験や、人々の予測や反応を裏切るような新しい表現の可能性を探求できます。
「読めるか読めないかギリギリの表現にしたり、インパクト重視で極端なデザインに振ったり。そうした“どう読み解くか”というパズルのような面白さには、わずかであればとても魅力があると思います」と、Monotypeのプロダクトデザイン・ディレクターであるJamie Neelyは語ります。線画に包まれた文字、あえて一部を欠けさせたフォント、あるいは常識外れの形で作られた書体など、それらの魅力の一部は、読み解くというプロセスそのものにあるのです。
とはいえ、ディスプレイフォントを用いて表現力を発揮できるとしても、実用性を考慮すべき場面もあります。スペースが限られているエディトリアルデザインや広告では、コンデンス体やコンプレスト体が有効です。ただし、適切なトーンの書体がなかなか見つからないこともあります。フォント選びでは縦横のバランス感も検討が必要です。アセンダー(文字の上に突き出た部分)やディセンダー(下に伸びた部分)が行間に干渉することもあるため、複数行でのテストを行い、重なりをチェックしましょう。ディスプレイフォントでは、この衝突を避けるためにではアセンダーやディセンダーが短く設計されていることもあります。さらに、単語をすべて大文字にし、アクセント記号(アキュートやウムラウトなど)を加えることで行間の干渉を確認できます。
一部のディスプレイ書体、特に可読性の限界に挑んだようなフォントは、扱いが難しいケースもあります。視認性をわずかに犠牲にすることで得られる読み解きの面白さと、単に“読みにくい”だけの表現とのあいだには、明確な違いがあります。どれくらいの文章を扱うのか、表示されるサイズや環境を考慮して判断する必要があります。
ディスプレイフォントは通常のフォントよりも注意深く使う必要がありますが、その手間に見合うだけの効果が得られます。うまく使えば、メッセージは見違えるように引き立ち、まったく違う印象を生み出したりすることさえ可能です。何よりもディスプレイフォントの魅力は、それ単体で力強く語れるという点にあります——まさに、フォントそのもののポテンシャルを引き出す存在なのです。
本動画はAdobe Max 2017にてライブ収録されました。Good Typeシリーズの続報をお楽しみに。